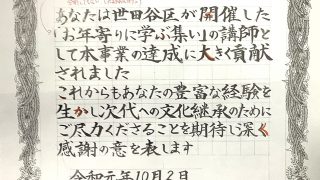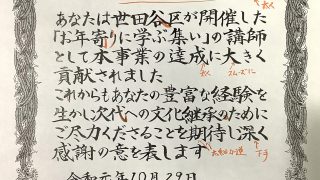昨日の稽古で、齋藤暖乃のお母さんから、先日の中体連大会での試合ぶりについて、質問された。
分け・分け・一本負けで副将にまわってきたが、一本取られて大将にまわせないことを最優先に消極的な試合となり、途中合議までかかってしまった(結局なにも反則はなし)。
スポーツマンシップに照らせば、勝ち負け云々よりも、とにかく「勝ち負けではなく、積極的に行け~」ではないのだろうか?…ということ。
その場では、それは「作戦としてはあり」と答えたが、ちょっと回答不足。
あらためて、下記のようにフォロー。
昨夜はちょっとグダグダだったので、フォローです。(長いです。)
副将に勝負がかかった場合、まず考えることは「チームが勝つためには、どのような展開にするのが良いか」です。
1本のビハインドなので、副将が引き分けでも大将が一本を取れば代表戦。
副将が1本勝ちすればタイスコアでの大将戦、2本勝ちなら大将は引き分けでもチームが勝ちとなり、大将の負担を軽くできます。
最悪なのは副将が負け、大将戦を待たずにチームの負けを決めてしまうことです。
暖乃は状況を理解しており、最悪のケースは避けるよう意識できていたと思います。
試合でダメなのは、「何も考えないで試合に臨むこと」です。順番にしたがって何となく試合されたのでは、チームメイトはたまりません。
ただ、タイスコアで大将にまわす方が良いのも明らかです。
生田が横山中の大将なら、一本リードでまわってきたら、無理な勝負はしないです。アドバンテージを生かし、相手が焦ってスキができるトコロを狙うくらいでしょう。
そう考えると「この相手なら、いけそう」という手応えがあれば、狙いを「引き分け」から「タイスコアで大将へつなぐ」に修正する勇気も必要です。
いずれにせよ引き分け狙いでも一本狙いでも、弱気や迷ってやると、逆に相手に一本を取られかねません。ギリギリの勝負では、本当に「強い心」が求められます。
横山中の副将の力量を覚えていないので、もっと積極的に行くべきだったかは何とも言えませんが、チームのみんなと一緒に勝つために、「できること・やるべきことを、しっかりやるぞ」という強い意識をもって試合に臨みたいものです。
その上でなら、結果はどうあれ、よくやったと言えると思います。
逆に「結果はどうでも良いから」が先にくると、先鋒・次鋒がそれほどの力量でもないのに、(結果として優勝するチームを相手に)何とか引き分けでつないでくれた勝負を、あっさり無下にすることにもなりかねません。
この辺の匙加減は、年齢や力量にもよります。小学校低学年にこれを要求しても理解できないし、先々伸びないので「目をつぶって、まっすぐ先に行け~」と言うことも多いでしょう。
あのチームなら圧倒的な実力はないけど、チーム力で粘り強く勝ち上がることもできそうです。本気で入賞を狙うことで、ひとまわり成長することも期待できます。
この辺は、(特に周囲が)目標と目的を勘違いしないことが大切です。
ちなみに、チームが「勝つなんて無理無理。さっさと終わって帰ろうよ~」みたいな雰囲気だったら、状況はまったく違います。引き分けなど考えず、自分だけのためにガンガンと行けば良いと思います。(だから環境も大事なんですね。)
気にされていたスポーツマンシップは、「相手選手をリスペクトする」ことだと思います。そこから、相手を軽んじてバカにした言動や規律を守らない行為は、スポーツマンシップから逸脱している、と言われます。自身にむかっては、「最善を尽くす」や「勝って奢らず」「勇気」などにつながってきます。
アドバンテージを利用して有利に進めるのは、戦術や試合運びの範疇であり、「スポーツマンシップに反する」とはちょっと違うかな、と思います。(今回はアドバンテージがあった訳ではありませんが。)
長文失礼しました。m(_ _)m