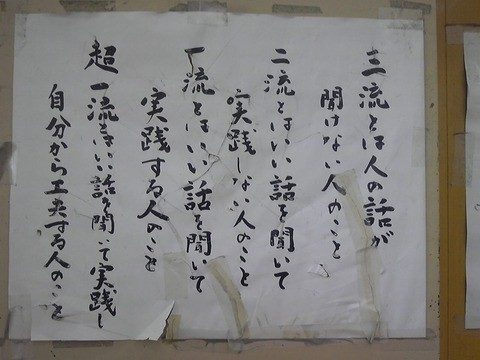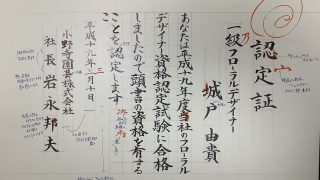翔き錬成会へ参加。ここへの参加も多くて、あと二回。
兵庫から神戸枝吉己勝館も参加。緑の風もいて、総勢200名以上。最大人数だった。午前中の団体戦は無しになって、ずっと個人戦だけ。午後はレクリエーションの後に、団体戦での錬成会。こちらは直心館との合同でやらせてもらった。
剣道時代の取材も来ており、そのうち掲載されるようだ。
もっぱら審判や運営にまわることになってしまい、午前中の試合はまったく見れず。午後の団体戦はついて回ったが、録画できたのは3試合のみ。(その分、じっくり見れるとも言えるが。)
【収穫】気がついたこと。
一本を打たれる場面として、相面・出端面を取られる割合が圧倒的に高い。ここへの対策が必須。
出遅れているというのもあるが、その前に足の前後幅が大きくなって、左足の蹴りのパワーがうまく体幹に伝わっていない。そのため、自分から行く場面は良いが、出端に対応する場面では出遅れたりすることが多い。相手が未熟で遅いなら、それでも良いが、相手の技量が上ってスピードもある選手には必ず乗られてしまう。
その場で点で合わせて対応できる場面であれば、合わせることで一本取れるようになりたい。現状では左足での支えが開いており、その場踏み込みで点であわせていては、当てるだけの開き打ちになってしまい、一本とはなりづらいだろう。
ただし足幅広めも悪い訳ではない。近間での攻防では、広めの方が良いだろう。遠間からの面の打ちあいの場合は、広めにしていたら跳べない。つまり最初は姿勢を大きく正しく整えるためにも狭め。近間での攻防では、多少は広めにして安定させる。
まずは、前後の足さばきをする際に、足幅が広くなりすぎないように。姿勢や視点の高さが変わらないように。左右の足幅が狭いので、前後に広げてバランスを取りやすくしている一面もあるかもしれない。
前後への移動で相手との位置関係を調整する。ここで視点が下がっていかないように。足の前後や左右の幅に気をつけて、前後や左右に足さばきで移動する。
攻め足などで左足を固定して、右足を出すこともあるので、そこは足幅が広くなるのも問題ないが、試合開始直後に立ち上がってすぐ、足幅が広くなるのは、良くない。
次に出端面のやり直し。相手の出にまっすぐあわせる。上から乗る。上からの軌道だけでなく、視点も上からなるように。見上げるように打たない。
打った後は、まっすぐ相手の正面にぶち当たる。
まずは元立ちは竹刀を少し開くようにして打ち、タイミングをとらえてまっすぐ打ち抜くようにさせる。左足の準備ができているようにする。
その後、前後のさばきも加えながら。
前にしっかり踏み切るパターン(自分が前に出ている)と、下がって相手を引き込むパターン(点でその場にて相手に合わせる)の2つか。
避ける場面でも、必ず左足が開いている。これは右足荷重になっていることも原因かもしれない。
小手返し面で、左足の向きをチェックか。
そこからガードからの、打突。そこでは足は開いているかもしれないが、極端にならないように。
※ 小さく小手面の追い込みも足が前を向いてないとできないので、取り入れての稽古ができるかも。姿勢を保つこと。小さい面の連続追い込みも良いか…。