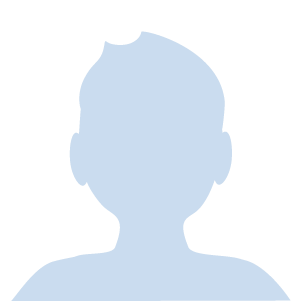木下大和が「楽しくない」という理由で、剣道をやめたがっているらしい。12/12(土)の稽古(終了時に到着)行った時に、篠先生と正座でお話ししていたので「何かな?」と思っていたが、お母さんからの報告を受けて、話しをしていたようだ。
何か他にやりたいことが有るという訳ではなく、言葉として出てくるのは「楽しくない」ということらしい。水曜日の大和担当としては、考えさせられる。
ただ、小学5年生が自分の中のモヤモヤを明確に言葉にするのは難しいだろう。「楽しくない」というのは、表層に出てきた言葉で実際には何かはよくわからない。勿論、いろいろなことの積み重ね、ということもあるだろう。
お母さんの話では、中学校剣道部の顧問が厳しい人に代わり、「坊主」にしなければならないらしい。それも遠因としてあるのかも、と。ただ、まだまだ先のことなのだから、目先のことが楽しくやれていれば、そんなことは言わない気がする。
水曜日の稽古としては、最近ちょっとマンネリ化していたかもしれない。先日も健志郎に
とも言われた。健志郎は、とにかく試合がやりたいようだったので、審査稽古のカタチではあるが地稽古をさせてみた。
木下さん(お母さん)が、そのまま「じゃあ、辞めましょう」とならずに踏ん張っている間に、何とかしたいトコロ。
- 裁量がない。自分で選べる余地が、ほとんど無い。言われたことを、やるしかない環境。
- 会話やコミュニケーションがない。稽古中は、ほぼ指導者との間のみ。場合によっては指導者からの一方通行のみ。
- 達成感がない。成功と失敗の明確な条件や、段階的な進歩を判断する材料がなく、自分では向上や成長を評価できない。
- 仲間が少ない、または居ない。喜怒哀楽を共感しあう仲間や好敵手がなく、一人ぼっちでやっている感。
ゲームが楽しいと感じる要素は、
- 一定のルール内で裁量が十分にある。
- その場で結果(評価)が出る。その理由もわかりやすい。
- レベルに応じて難易度が上がり、適度に手応えがある。
- サプライズがある。
- 明確な目標がある。
- 目標を共有できるネットの友人?と、コミュニケーションをとりながら連携プレーし、成功や失敗を共有/共感できる。
夢中にさせる仕掛けがあるので、自然と腕前も上がるという訳か。
ただしゲームは「遊んでいる」というよりも、与えられて「遊ばれている」という側面もあり、主体性は育ちにくい。
剣道は「習わないと、できるようにならない」とも言われる。それが上位者の既得権益を守るための言い訳のような気もするが、真実の一面であることも確か。下手では、楽しく打ち合うことや勝負をすることはできない。なので、かなり絞った内容に限定して身に付けさせようと思っているのだが、一方通行であったことは間違いない。
試合や審査もあるので、これからの2回は自分達でやりたいことを決めさせる時間を設けるか?