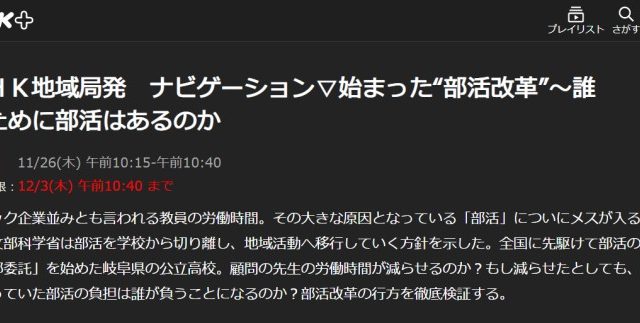結局、力をつけていくのは、自発的内発的な動機がないと、何を言っても響かない。
最後は人間力。それをわかっているから、寮生活などで挨拶や規律、清掃、靴を揃えるといったトコロから始める。そうやって人間力を高めながら取り組んでいくので、一流のアスリートは現役を引退してもやっていける。
一方で、何も考えずにギューギューやられてトップになる人間もいる。そういう人は引退後に「お騒がせ」になったりする。
剣道は個人競技だが、オープンスキルが必要とされる。相手との関係性の中で、技術を使い、身体を動かす。
勉強はクローズドスキルが中心。学校や塾で与えられたカリキュラムでの授業を吸収するだけでは、クローズドスキル。要望を出したり、質問力を向上させていくことが、オープンスキル。受験はクローズドスキルだけで、ほとんどクリアできる。
オープンスキルを磨くには、面倒くさい。脳を使って考え、相手とコミュニケーションをとり、場合によっては評価をする必要がある。試行錯誤で多くのエラーをすることは恥ずかしいことでもなんでも無いが、そこへの評価と改善をしようとすると脳が疲れる。ただ打っているだけの方が「気が楽」だが、これはクローズドスキルになってしまう。
こういったことは、人間力が必要になってくる。
だから、面や胴打ちはそれなりだが、小手や逆胴になると突っ込みすぎという相手との関係性(間合い・距離感)が出てくるので、とたんにできなくなる。
生田がやかましく、山田が耳障りよく言っていることは、今の時期はオープンスキルに関することが多い。これがちょっとやって上手くいかないと、楽な「ただ打つだけ」の稽古の方に流れてしまう。
このままだと稽古時間が短くなる場合、密度を上げるのではなく、時間にあわせて内容を減らす方向になるだろう。短時間に出し切る、という稽古ができなければ、試合時間の中でもサラ~っと過ごすようになり、取りに行かねkればならない試合になったりすると、すぐに息が上がってしまうだろう。
こういった取り組みをもっとお互いに話してほしいものだが、「ミーティング」というと形式張って意見は出なくなる。合宿中はちょっと部屋の中で、ということもできるだろうが、そういった話しは普段の会話の中でボケとツッコミをやりながらで、やりあって欲しいものだ。
合気になっての稽古や、かけひきのシミュレーションによる稽古、フェイントでの稽古には、相手とのコミュニケーションや要求・評価・改善のトライアルが繰り返し必要となってくる。これが面倒くさい、苦手、ということになる。すぐに成果が出ずカット&トライが必要なのだが、すぐに結果が出ないため「無駄」と諦めて、「気が楽」な「ただ打つ」だけの稽古になってしまう。だから本質に迫ったり、上達することができない。脳みそが汗をかかないから、ただの運動になってしまう。スポーツは、高度で知的な活動でもある。こうして、人間が変わり、部活動の集団じたいが変わっていかないと、質的に化けていかない。成長しない。つまり価値を感じない。
以前に素振りでの気の抜けたような声を注意したが、「出し切る」ということができない訓練になっている。それは変わったか?やはり自分で意識を持っていないと、流してしまう。
…それも指導力のうちか。無理にでもやらせて成果を出せば、勢いがつくか?最初はそれが必要?