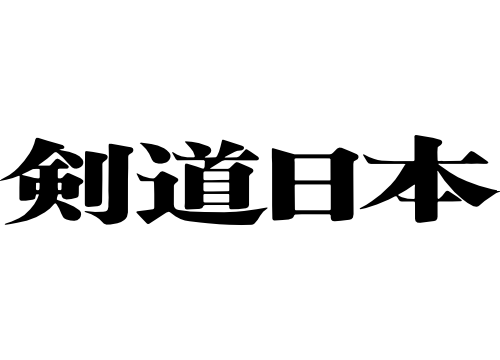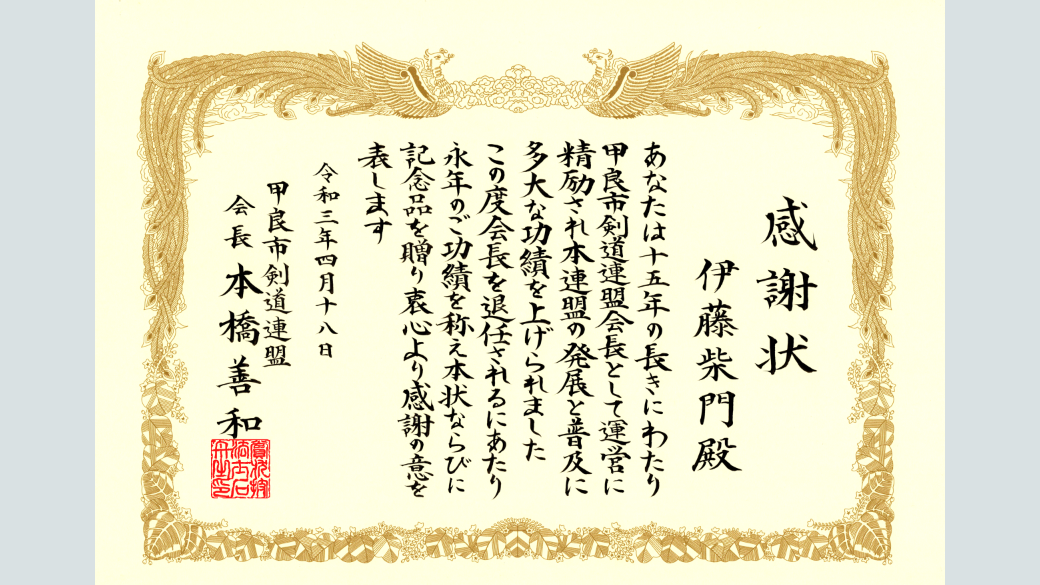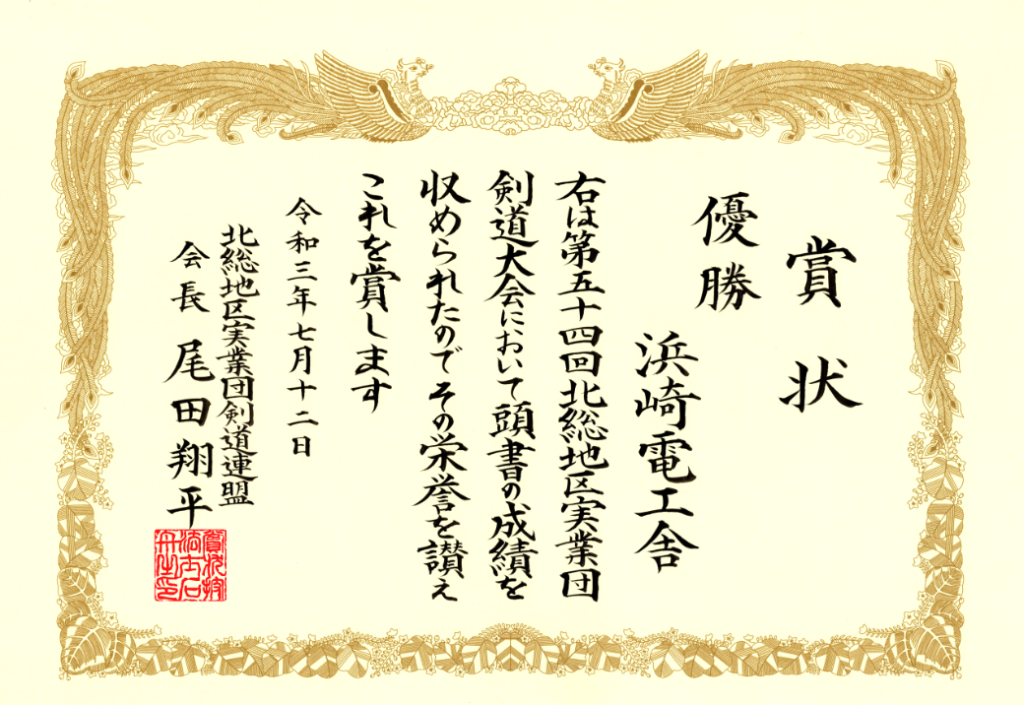相面の憂鬱
審判をやっていて、一番泣きたくなるのは互角の相面ではないでしょうか。
相打ちはない?
全剣連の発行している「剣道試合・審判・運営要領の手引き」によると「相打ちはまず無い」とされています。
たしかにミリ秒単位の世界にまでいけば、同時はないでしょう。
ただ、見た目としては「同時」に見える相打ちは往々にしてあるものです。
どちらも見事な打突をしていて、それぞれ単独の打突であれば有効打突の要件を満たしていたら、「相打ちはない」のであれば、どちらかが有効打突となります。
真剣なら双方の胴体が勢いよく出ている面を打っている状態での「ほぼ」相打ちなら、共倒れとなるでしょうが、竹刀剣道での判定は「両者負け」という訳にはいきません。
どう判定しているか
「勝って打った」方に旗を上げることが多いです。先をかけ中心を取っているなど攻め勝っていたり、打突での勢いが勝っている方に旗を上げます。
格上の打突をした方に旗が上がりやすいと思います。
そういった意味では、それまでの試合の流れや、着装などで格上の印象を与えることは有利に働くと思います。また、身長の高い方が有利だというのも否定できません。
ただ攻め勝っていたり、うまく相手を引き出していても、相面で中心を割られていると判断したら、いくら勢いがあっても相手方の方へ旗を上げます。
打突に時間差があったと感じた場合は、後に打った方が格上であっても、先に打った方が有効打突の要件を満たしていれば、先に打った方へ旗を上げます。これは当たり前ですね。
それに、面に当っていることが大前提です。一方の打突が「実は当たっていませんでした」ということも、意外とあるものです。選手は「やられた」と思っていても、打ち切った形を作り、「自分が取った」というアピールをします。ここはしっかりと見極めたいですが、位置が悪いと区別できない場合があります。
相面を判定するには、審判も試合の流れを先読みしながら、一瞬でも気を抜かないように攻防の機微を見定めなければならないと思います。
苦い思い出
「選手が肚を決めて勝負に出た相面の判定から、逃げてはダメだ」
もう30年くらい前でしょうか、ある大会で審判主任の先生に言われたコメントです。当時の僕は五段で副審。主審も僕と同じようなレベルの方。もう一人の副審は…、失念してしまいました。
高校生の試合で双方が相面に跳んだ時のことです。背の高さもあまり違いがなく、同格・同時で見事な打突だったと思います。もう一人の副審の方がどちらかに旗を上げたのだと思いますが、僕はどちらの有効打突かまったく見分けられず、「どちらも無効」として旗を振りました。主審も同じだったので、試合は継続されました。
今となっては団体戦か個人戦だったかも定かではありませんが、勝負のかかった場面での相面に試合場の周囲も盛り上がったのだけは覚えています。
試合終了後に3人の審判員が戻った時、審判主任の先生に冒頭の言葉を言われました。「キビシ~」とは思ったものの、まったくその通りだと感じました。今でも、そう思います。
それからは見事な相面に対しては、明らかな時間差がなければ総合的に判断して、「こっちだ」と見た方に思い切って上げるようにしています。他にも二人の審判がいるので「間違っていたら、消すなり反対へ上げるなりしてくれぇ~」という気持ちもあります。
しかしながら試合後に「あの判定は逆では?」等と言われ、頭を抱えることもあります。「もっとしっかり見極めなければ」と反省しきりです。
いつ相面が来るかということにも頭において、審判に立つように心がけています。だいたい迷う時は、気を抜いたつもりはなくても「眺めているだけだった」と振り返ることが多いです。試合者も真剣なら、審判員もそれ以上に真剣でなければなりませんね。